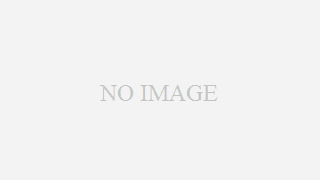 言葉の意味
言葉の意味 MMF(えむえむえふ)
MMFは「マネー・マーケット・ファンド」の略で、短期的な金融商品に投資する投資信託の一種です。MMFは通常、安全性が高く、流動性の高い金融商品を対象とし、主に短期国債やコマーシャルペーパー(企業が発行する短期債券)などが投資対象です。リスクが低いため、元本を維持しながら安定的な利回りを得ることが期待される商品です。
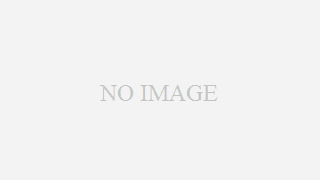 言葉の意味
言葉の意味 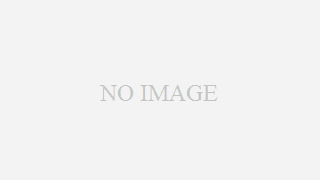 言葉の意味
言葉の意味 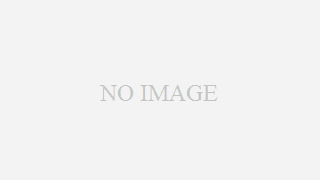 言葉の意味
言葉の意味 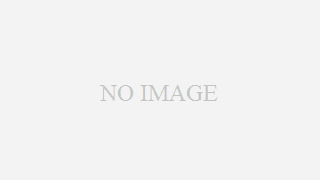 言葉の意味
言葉の意味 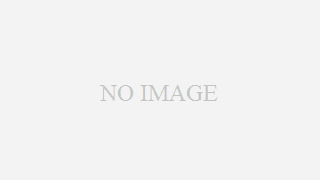 言葉の意味
言葉の意味 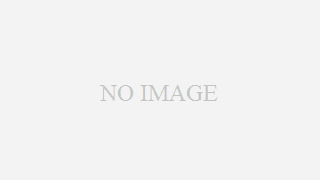 言葉の意味
言葉の意味 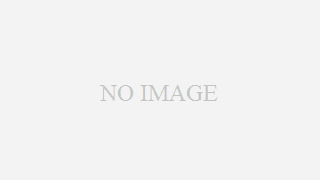 言葉の意味
言葉の意味 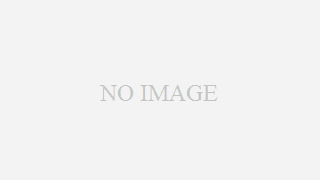 言葉の意味
言葉の意味 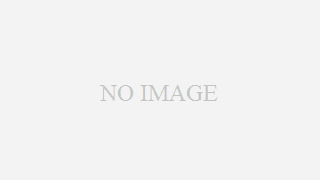 言葉の意味
言葉の意味 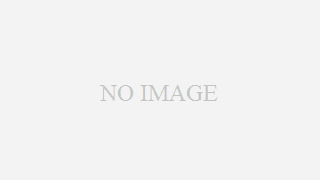 言葉の意味
言葉の意味