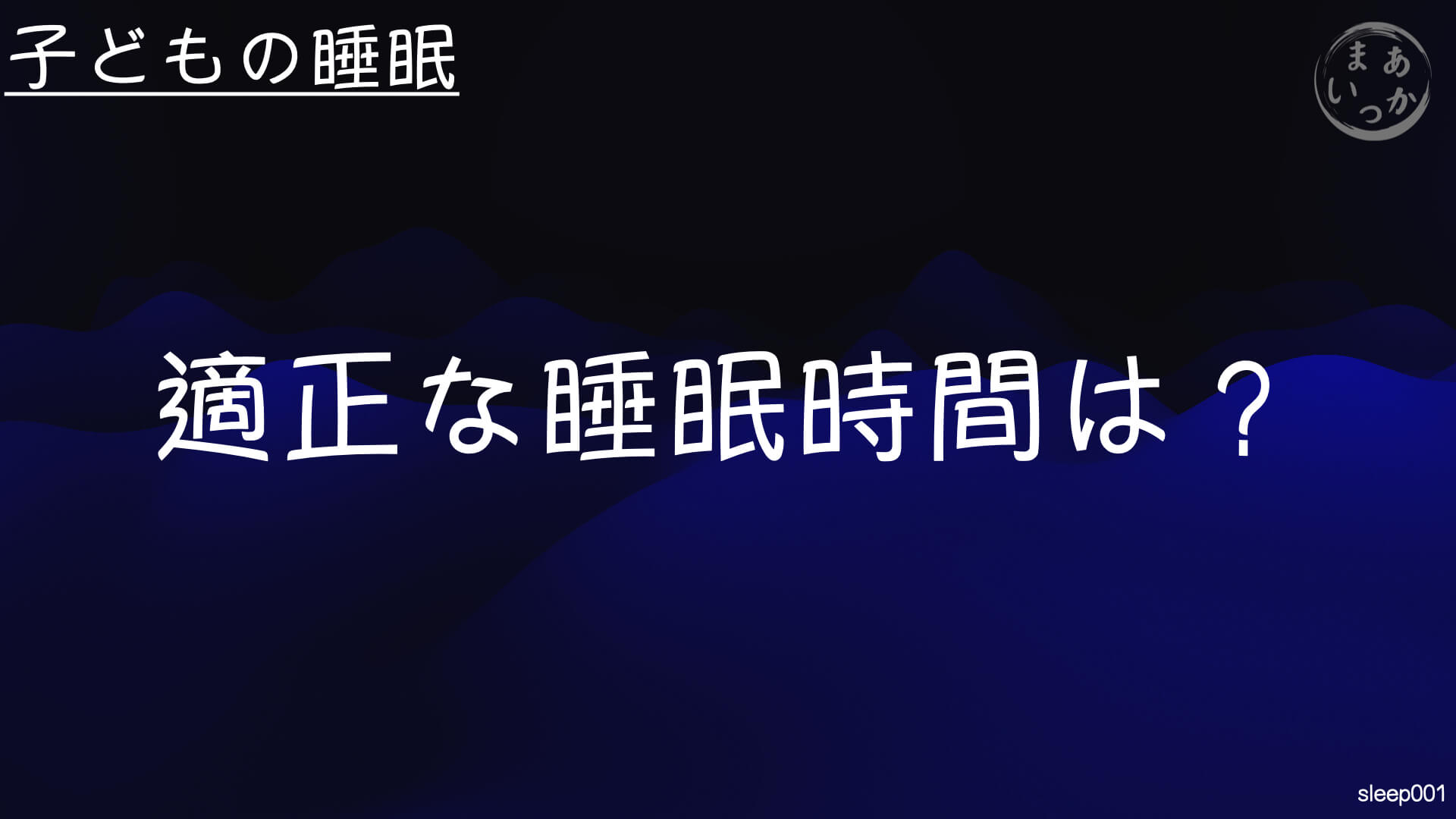子どもの睡眠時間の目安は?年齢別の適正時間と寝かしつけのコツも紹介
夜、ようやく子どもが寝てくれて、やっと一息。
そんな瞬間に、「今日はちゃんと眠れてたかな?」「最近寝るのが遅いけど、大丈夫だろうか。」と、ふと不安になること、ありませんか?
毎日忙しい中で、つい「まあいっか」と流してしまうこともあるけれど、子どもの睡眠って、心と体の成長に本当に大切な時間。
だからこそ、ふとした瞬間に気になってしまうんですよね。
「他の子と比べて寝る時間が遅いかも。。。」
「うちの子、昼寝が長すぎるんじゃないかな?」
「夜中に何度も起きるけど、これって普通?」
そんな悩みや疑問を抱えながらも、「育児に正解はない」「個人差がある」と言われると、どうしたらいいか余計にわからなくなってしまう。
ネットで検索すれば膨大な情報が出てくるけれど、それが我が子にとって本当に合っているのか、自信が持てなくなることもありますよね。
そこで今回は、「子どもの適正な睡眠時間」について、わかりやすく丁寧にまとめてみました。
年齢ごとの目安や、睡眠不足がもたらす影響、そして睡眠習慣を整えるためにできることなど、日々子どもと向き合っている親だからこそ気になるポイントを中心にお届けします。
忙しい毎日の中でも「これだけは押さえておきたい」という情報を厳選していますので、ぜひご覧いただければと思います。
「うちの子にとって、どんな睡眠が“ちょうどいい”のか?」
そんなヒントが見つかる時間になれば嬉しいです。続きをぜひご覧ください。
私は2児の父で、現在は会社員として働きながら、平日の夜や週末に育児に奮闘中です。
最初はオムツ替えに四苦八苦していましたが、少しずつ子どもと向き合う時間が楽しくなり、気づけば寝かしつけのプロ(?)になっていました。(子どもより先に寝てしまうこともありますが。。。)
完璧な育児じゃなくても大丈夫。肩の力を抜いて、ちょっとしたヒントや共感を見つけてもらえたら嬉しいです。
*執筆時は長男2歳、次男0歳です。
子どもの睡眠時間の目安って?年齢別にチェック!
わたしたち人間は、人生の3割程度を睡眠に費やしています。
80歳まで生きたとすると、なんと27年くらいは寝ていることになります。
なんかもったいない気がしますが、寝ないなんて、考えられないですねよ。。。
そんなわたしたちの適正な睡眠時間はどれくらいでしょうか。
表1(年齢別推奨睡眠時間)| 年齢 | 推奨睡眠時間(時間) | 補足説明 |
|---|---|---|
| 0〜3か月(新生児) | 14〜17時間 | 昼夜の区別がなく、数時間ごとに起きる |
| 4〜11か月(乳児) | 12〜15時間 | 夜にまとまって眠るようになる |
| 1〜2歳(幼児) | 11〜14時間 | 昼寝は1〜2回。生活リズムが安定してくる |
| 3〜5歳(幼児) | 10〜13時間 | 昼寝が減少し、夜間の睡眠が中心になる |
| 6〜13歳(小学生) | 9〜11時間 | 成長ホルモンの分泌が活発な時期、質の良い睡眠が重要 |
| 14〜17歳(中高生) | 8〜10時間 | 学校や部活で忙しくなるが、睡眠不足に注意が必要 |
表1を見たら一目瞭然ですが、子どもの適正な睡眠時間は、年齢ごとに大きく異なります。
例えば新生児(0〜3か月)は14〜17時間と長く、これは脳や体の基礎的な成長が活発に行われているためです。
月齢が進むにつれて徐々に睡眠時間は短くなりますが、それでも乳児期(4〜11か月)は12〜15時間、幼児期(1〜2歳)でも11〜14時間が目安とされています。
3〜5歳になると昼寝の頻度が減り、夜間睡眠が中心となりますが、10〜13時間程度の十分な睡眠が必要です。
小学生(6〜13歳)になると活動量が増え、9〜11時間の睡眠で心身のバランスを保つことが大切です。
中高生(14〜17歳)は8〜10時間とさらに短くなりますが、成長ホルモンの分泌や集中力の維持のために、質の高い睡眠を確保することが求められます。
わたしの子どもは、表1の適正睡眠時間と比較してみるとどうでしょうか。
表2(長男・次男の睡眠時間)
| 項目 | 年齢 | 適正な睡眠時間(目安) | 実際の睡眠時間 |
|---|---|---|---|
| 長男 | 2歳8か月(幼児) | 11〜14時間 | 夜:11.5時間(20:30〜8:00) |
| 次男 | 1歳0か月(乳児) | 12〜15時間 | 夜:11時間(20:00〜7:00)昼:2時間 |
長男は2歳(8ヶ月)なので、表1で分類する適正な睡眠時間は11〜14時間くらいです。
普段は20:00になったら、おもちゃを片付けて、歯磨きして、布団に入ります。大体20:30には寝ているでしょうか。
起床は大体8:00くらいなので、睡眠時間としては、11.5時間ですかね。
次男は1歳(0ヶ月)なので、表1で分類する適正な睡眠時間は12~15時間くらいです。
長男と同じように20:30には寝て、同じように起きます。明け方の30分くらいはミルクで起きるので、夜の睡眠時間としては、11時間ですかね。ただ次男の場合は、日中2時間くらいお昼寝をするので、合計の睡眠時間は、13時間くらいでしょうか。
2人とも、大体は適正な睡眠時間を取れていますね!
皆さんもご経験があると思いますが、例外は沢山ありますので、あくまで【大体は】です。
布団に入ったのに、横で踏ん張って、うんちをしている。。。
おしゃぶりがどこかへ消えた。。。泣いている。。。
なんやかんやで、寝る時間はどんどん遅くなっていきます。なので、【大体は】で大丈夫だと思ってます。
睡眠不足が子どもに与える影響とは?
子どもだから寝なさい。寝る子は育つ。と教わりながら成長してきた、わたしです。
実際のところ、睡眠不足が子どもに与える影響には何があるのでしょうか。
精神的・認知的な影響
- 子どもが睡眠不足になると、集中力の低下や記憶力の低下、情緒不安定など、日々の生活に深刻な影響が現れるようです。
- 特に、睡眠不足が続くと、脳の発達領域に悪影響があり、意思決定や抑制機能、ワーキングメモリに支障が出ます。
- 例えば、米国のABCD研究では、9〜10歳の子どもが毎晩9時間未満の睡眠だったグループは、2年間にわたって注意力や記憶力の低下が続いたと報告されています。
- また、乳幼児でも夜間の目覚めや睡眠の断片化が続くと、その翌日の集中力や学習力に悪影響があるとされています。
- 行動面でも、「ぼんやりする」「忘れ物が増える」「感情の切り替えが苦手になる」といった変化が現れます。
- 情緒面では、イライラしやすい・泣きやすい・癇癪を起こしやすいなど、穏やかさが失われ、心の安定を保つのが難しくなります。さらに、記憶の定着や言語習得にも支障が出るため、幼児教育や家庭学習における学習成果にも影響が及びます。
- こうした精神的・認知的な影響は中高生にも見られ、学校生活における注意力の低下やうつ・不安傾向の増加に繋がるとされています。そのため、十分な睡眠を習慣化することで、子どもたちの発達を支えることがとても重要です。
身体的な影響
- 子どもの睡眠不足は、身体の成長や健康維持にも深刻な影響を及ぼすようです。
- まず、成長ホルモンの分泌が夜間の深い眠りに集中するため、十分な睡眠が確保されないと、身長や骨・筋肉の発達に影響が出ます。
- 特に乳幼児や学童期は、成長ホルモンの分泌が盛んな時期であるため、睡眠時間が減ると発育のリズムが乱れることがあります。
- また、睡眠不足によって免疫機能が弱まり、回復力も低下するため、風邪や感染症への罹患リスク増加が指摘されています。
- 加えて、睡眠障害は肥満リスクと関連し、ホルモンバランスの乱れにより、食欲が増加しやすくなるほか、代謝異常も引き起こされがちです。
- さらに、心臓や代謝系にも負担がかかる可能性があり、将来的な生活習慣病のリスク(高血圧、糖尿病など)を高める要因となります。
- このように、質と量の両面で良い睡眠を維持することは、子どもの健康な成長と免疫力、その後の生活習慣形成にも大きく影響します。
長期的な影響
- 子どもの睡眠不足が慢性化すると、学業成績や心の健康、社会性の発達などに長期的な悪影響をもたらすようです。
- たとえば、睡眠が不十分だと学力低下・集中力の散漫・記憶力低下といった学習面への影響が明瞭になることが、多くの研究で相関が報告されています 。
- さらに、感情や行動面では、うつ、不安、攻撃性、衝動性、ADHD傾向などが増加するリスクがあります。長期的な睡眠問題は情緒不安定・社会適応の難しさなどを引き起こしやすく、子ども本人の成長や家庭・学校生活にも影響が広がります。
- また、社会性の発達にも支障をきたし、友だちとの関係性や協調性に問題が生じやすくなります。さらに、ADHDや反抗挑戦性障害(ODD)との関連も長期的には無視できず、睡眠不足が行動障害の一因になる場合もあると報告されています。
- 米国Child Mind Instituteなどは、中高生において睡眠不足がうつ病や自殺リスクの増加と関連していると警鐘を鳴らし、学業と睡眠のバランスが将来の人生設計に大きく影響することを示唆しています。
- つまり、子どもの睡眠は“今日だけの問題”ではなく、将来に向けた心身と社会性の基盤を育む重要な要素です。長期にわたって不十分な睡眠が続かないよう、生活習慣や環境の見直しが必要です。
- 睡眠不足は【精神的・認知的な影響】【身体的な影響】【長期的な影響】があるようです。
このような情報を聞くと、怖くなりますよね。
頑張って、子どもを寝かしつけようとするけど、寝てくれない。
だんだんとこっちもイライラしてくる。
わたしもこのような経験があります。
強く怒ってしまったこともあります。
でもこれだと悪循環です。
わたしは、子どもの間はすべてが準備期間だと思うようにしました。
最初からできる子どもなんていないと思います。
なかなか寝てくれないのは、しっかりと睡眠を取れるようになるための、準備期間だからです。
まだ会話ができないけど、本人も本当は寝たいと思っているのかな。
一生懸命、寝ようと頑張っているのかな。と考えると、優しく接することができるようになりました。
寝るまでの習慣をつける
こうしたら絶対寝る!とか、寝かしつけの裏技!とか言っている人もいますが、わたしは、あまり信用していません。
試してみるのは全然ありだと思いますが、寝てくれたらラッキー!くらいの感覚の方が良いです。
次男が生まれてから、身をもって経験しましたが、兄弟ですら全然違います。
長男はよく寝る子です。1歳くらいから夜泣きが少なくなり、夜寝たら朝まで起きないことが多かったです。
一方で次男は、ほぼ100%夜中に起きます。
兄弟でもこんなにも違うんだから、他の子とはもっと違うと思います。
わたしたちがやっているのは、布団に入るまでを習慣化するくらいです。
布団に入ってからは、横で寝ているだけです。
寝る前の習慣化
国立保健医療科学院は、適切な睡眠と規則正しい生活習慣が発達と肥満予防に欠かせないと指摘しています 。
Sleep Foundationも、ルーティンを守る子どもは寝つきが早く夜間覚醒が少なく、睡眠時間が長いと報告しています 。
1万人超を対象にした国際調査では、週5回以上のルーティン実施で就寝時刻が早く、睡眠が1時間以上延びる「用量反応関係」が認められました 。
最新レビューも、安定したルーティンが睡眠だけでなく情緒・認知発達、親子関係を高めると結論づけています 。
3〜5歳は1日11〜13時間の睡眠が推奨され、就寝前の静かな遊びと電子機器オフがメラトニン分泌を助けると示されています 。
夕食→入浴→絵本→消灯といった手順を毎日同じ時刻に繰り返せば、「もうすぐ寝る時間」と子どもが安心し、健やかな成長を後押しできます。
出典:国立保健医療科学院、Sleep Foundation、国際調査
わたしたちの場合は、20:00から片付け→歯磨き→就寝 だけをやっています。全部で10分くらいで終わるので、布団に入って、子どもたちが寝るのは、早くて20:30くらい、遅くても21:00です。
当然、寝てくれないときもあります。トントンしたり、抱っこしたり、色々試してダメなときは、もう1回遊びます(笑)
だから、22:00くらいになることは普通にあります。
大人でも疲れてなければ、なかなか寝れないですよね。たぶん、子どもたちも遊び足りなかったんだと思います。
あまり、悩み過ぎないことを大切にして、育児に励んでいます。
よくある睡眠の悩みQ&A
子どもの睡眠に関するよくある質問と、それぞれの回答の信頼できる出典を記載しておきます。
出典は主に日本小児科学会、厚生労働省、米国睡眠財団(NSF)などの公的・専門機関から引用しています。
年齢ごとの推奨睡眠時間は以下の通りです。
- 1〜2歳:11〜14時間
- 3〜5歳:10〜13時間
- 6〜12歳:9〜12時間
- 13〜18歳:8〜10時間
出典:National Sleep Foundation「Sleep Duration Recommendations」、厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2014」
3歳頃までは昼寝が発達に有益とされ、4〜5歳になると必要性が減っていきます。
出典:日本小児保健協会「幼児の睡眠と発達」、国立研究開発法人国立成育医療研究センター
原因としては、生活リズムの乱れ、就寝前の過剰な刺激(テレビ・スマホ)、昼寝の時間帯などが考えられます。
出典:厚生労働省「子どもの睡眠習慣に関する調査」、日本睡眠学会「子どもの睡眠に関するガイドライン」
特に夕方の遅い時間に長時間寝ると、夜の入眠を妨げる可能性があります。
出典:日本小児科学会「子どもの睡眠と生活リズム」、National Sleep Foundation「Napping Guidelines」
ルーティン(お風呂→絵本→消灯など)を毎日同じにすることで、入眠のスムーズさが増します。
出典:厚生労働省「健康日本21(第二次)」子どもの睡眠習慣、日本小児科学会 乳幼児の睡眠衛生に関する提言
乳児では正常な範囲ですが、成長とともに夜間覚醒が多すぎる場合は睡眠環境の見直しが必要です。
出典:国立成育医療研究センター「睡眠の基礎知識」、日本睡眠学会「睡眠障害国際分類」
短期的には問題ありませんが、依存が強くなると一人で眠る力が育ちにくくなるため、段階的な卒業が勧められます。
出典:日本小児科学会「乳児のセルフスリープに関する提案」、American Academy of Pediatrics「Healthy Sleep Habits」
「社会的時差(ソーシャル・ジェットラグ)」が起こり、体内時計が乱れやすくなるため、毎日同じ時間に寝起きすることが望ましいです。
出典:日本睡眠学会「生活リズムの重要性」、Sleep Foundation「Social Jet Lag and Sleep Consistency」
完璧じゃなくていい
育児は「完璧」である必要はありません。
むしろ、すべてを完璧にこなそうとすると、心も体も疲れてしまいます。
子どもにとって大切なのは、親がいつも笑顔でそばにいてくれることと、安心できる存在であることです。
少しくらい失敗しても、うまくいかない日があっても大丈夫。
それが人間らしくて、子どもにとっても良い学びになります。
頑張りすぎず、肩の力を抜いて、「まあいっか」と笑えるくらいがちょうどいい。
あなたが毎日を一生懸命に生きているその姿こそが、子どもにとって最高のお手本です。
どうか、自分を責めず、自分を認めてあげてください。
完璧じゃないからこそ、育児にはあたたかさがあるのです。
というのも、わたし自身、次男が生まれたときに、精神的に参ってしまった経験があります。
出産してから1ヶ月後くらいに、妻が病気で数日間入院することになりました。
長男だけなら、余裕でしたが、2人となると大変。。。
完璧を求めるがゆえに、精神的にも肉体的にも、落ち込んでしまいました。
だから、育児は【大体】で良いし、【まあいっか】が必要なんです。
まとめ
子どもの睡眠は、年齢ごとに必要な時間が異なり、心身の成長に深く関わる大切な要素です。
睡眠不足は、集中力や情緒、成長ホルモン、免疫力にまで影響し、将来的な健康や学業にも関係します。
一方で、理想的なリズムに毎日ぴったり当てはめるのは現実的ではなく、日によって違っても「大体OK」で十分です。
兄弟でも個性があり、寝方も違います。大切なのは、習慣づけと親子の安心感。
完璧な育児より、笑顔で寄り添う姿こそが、子どもにとって一番の安心です。
「まあいっか」で、ゆるやかに育児を楽しんでいきましょう。
でも、今の生活リズムをいきなり大きく変えるのは、子どもにとっても大人にとっても負担が大きいものです。
「早く寝かせなきゃ」と思えば思うほど、うまくいかないこともありますよね。
そんなときは、焦らず、少しずつで大丈夫です。
まずは寝る前の過ごし方を整えたり、毎日10分ずつ早めてみたりと、小さな工夫の積み重ねで生活リズムは自然と整っていきます。
子どもも、親の気持ちを敏感に感じ取るもの。
大切なのは、無理をせず、親子で心地よいペースを見つけることです。
「昨日よりちょっと早く寝られたね」そんな小さな変化を喜びながら、ゆっくり進んでいきましょう。
おわりに
子どもの数だけ、睡眠スタイルも育児の形も違います。
正解が見えにくいからこそ、「知って」「試して」「わが家に合う方法を見つける」というプロセスがとても大切です。
うまくいかない日があっても、「まあいっか」と笑って、次の日にまた少しだけ工夫してみる。
それだけでも、親子にとって大きな一歩です。
焦らず、比べず、少しずつ。
そうして積み重ねていく日々が、子どもにも自分にもやさしい育児につながっていきます。
このブログが、ほんの少しでもあなたの気持ちを軽くするきっかけになれたら嬉しいです。
今日もおつかれさまでした。
.png)